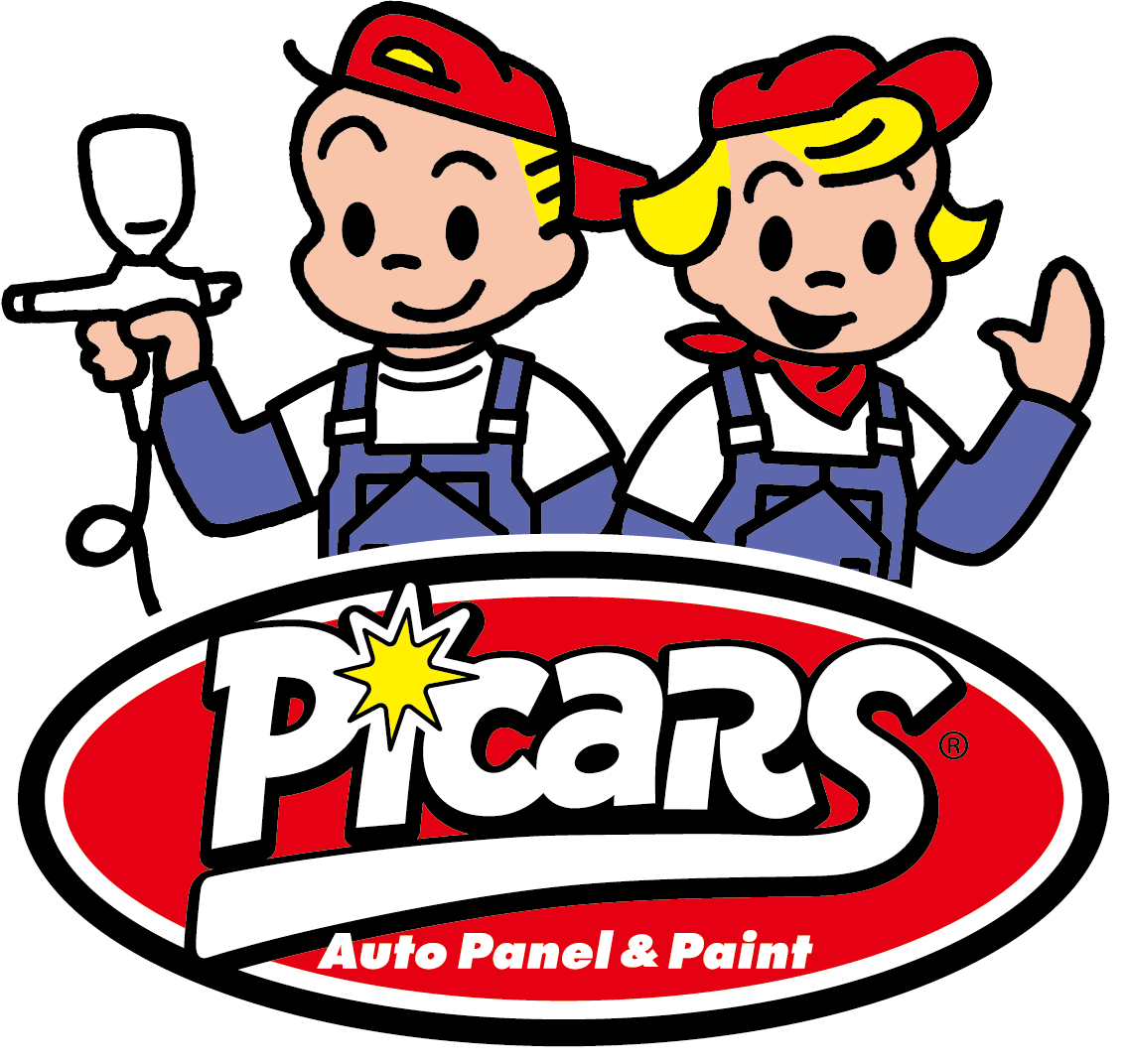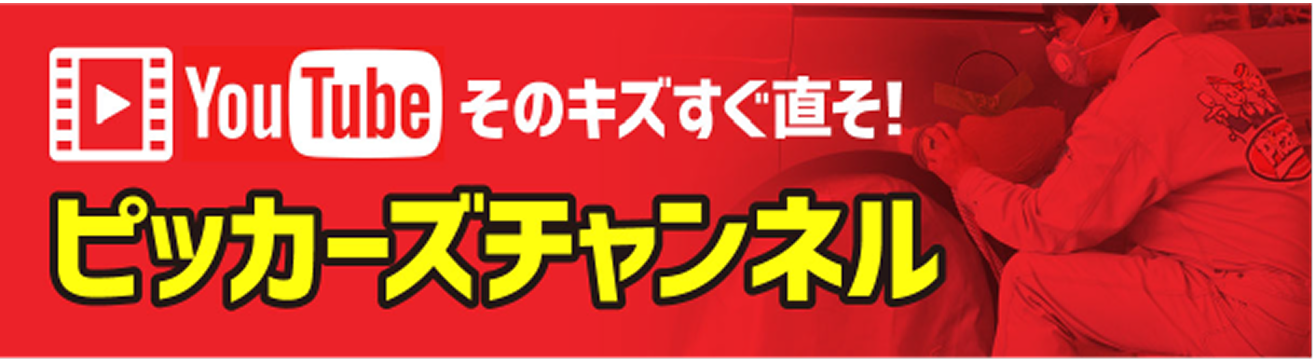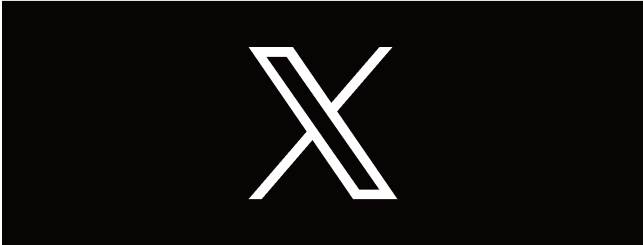車の修理代は経費でいくらまで認められる?注意点と一緒に解説

事業用で使う車を所有している方なら、車の修理代は経費で落とせるのか、一度は気になったことがあるのではないでしょうか。経費として計上できる金額が多ければ、その分課税対象となる所得を減らせて、節税にもつながります。
ただ一方で「できるだけ経費にしたいけれど、処理の仕方を間違えて税務署に指摘されないか心配」という不安を持つ方も少なくありません。
この記事では、車の修理代を経費として計上できる範囲や注意点を紹介します。また、損害賠償金を経費にする際のポイントも解説しているため、ぜひ参考にしてください。
車の修理代は経費でいくらまで認められる?
事業で使っている車の修理代は、基本的にはその年の経費として処理できます。多くの場合、修繕費として計上しますが、修理の内容によっては一度に全額を経費にできる場合と、数年に分けて少しずつ費用化しなければならない場合があるため、注意が必要です。
修繕費にあたるのは、車をもとの状態に戻すための修理や、日常的な維持管理に関わる出費です。
具体的には次のようなものが該当します。
●擦り傷やへこみを直す板金修理
●タイヤの交換
●バッテリー交換
●オイル交換
●ブレーキパッド交換
これらはどれも車を元どおりに使える状態に戻すための支出となるため、その年の経費にまとめて計上できます。
一方で、修理や交換によって車の寿命を延ばしたり、性能を向上させるような出費は資本的支出と呼ばれます。この場合は修繕費にはできず、いったん固定資産として計上したうえで、耐用年数に応じて減価償却で分割します。
例としては次のようなものがあります。
●特殊な改造を行った場合
●本来の性能より大幅に高い部品へ交換した場合(その性能アップ分の費用)
ただし、すべての資本的支出が減価償却になるわけではありません。次のようなケースでは、資本的支出にあたるものであっても修繕費として一括で処理することが認められています。
●1回の修理費が20万円未満の場合
●3年以内ごとに定期的に行われる修理の場合
つまり、金額が少額だったり、定期的に繰り返し行うような修理やメンテナンスであれば、その年にまとめて経費にできます。
出典:国税庁「No.5402 修繕費とならないものの判定」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm)
車の修理代に用いる勘定科目と仕訳例

車の修理代を経理処理するときに使われる代表的な勘定科目は、修繕費、車両費、雑損失の3つです。どの科目を選ぶかによって仕訳の仕方も変わるため、それぞれの特徴を知っておくと「この場合はどの科目にすればいいのだろう?」と迷うことが少なくなります。
ここでは、それぞれの勘定科目の違いと具体的な仕訳例を解説します。
修繕費
もっともよく使われるのが修繕費です。固定資産(車・建物・機械など)をもとの状態に維持・管理するための支出を記録する勘定科目です。
たとえば、壊れた部分を直したり、古くなった部品を交換したりする費用が該当します。具体的には、エンジンやブレーキの修理、板金塗装で車体を直す費用、消耗した部品の取り替えなどが代表例です。
【仕訳例】
修理業者に20,000円を現金で支払って修理した場合
(借方)修繕費 20,000 /(貸方)現金 20,000
車両費
車両費は、車に関わるさまざまな支出に幅広く使える勘定科目です。修理代はもちろん、ガソリン代、駐車場代、洗車代なども含まれます。使いやすい科目ですが、ひとつ注意点があります。
それは、毎年違う科目で処理しないことです。ある年は修繕費、翌年は車両費といったようにころころ変えると、数字の比較が難しくなるだけでなく、税務署から指摘を受ける可能性があります。科目は一度決めたら基本的に統一して使うのが基本です。
【仕訳例】
クレジットカードで修理代200,000円を支払った場合
カード利用時
(借方)車両費 200,000 /(貸方)未払金 200,000
口座引き落とし時
(借方)未払金 200,000 /(貸方)普通預金 200,000
雑損失
雑損失は、日常的な修理や維持費ではなく、突発的に発生した損害を処理するための科目です。たとえば、従業員が業務中に交通事故を起こし、相手の車を壊してしまい、その修理代を会社が負担した場合などです。
自社の車ではなく、他人の財産に対する賠償をするときに使います。
【仕訳例】
事故で相手の車の修理代100,000円を現金で支払った場合
(借方)雑損失 100,000 /(貸方)現金 100,000
このような支出は修繕費や車両費には当てはまらないため、雑損失で処理するのが正しい方法です。
車の修理代を経費計上する際の注意点
車の修理代はすべてがそのまま経費になるわけではありません。経費として処理するときには、いくつかのルールや注意点を押さえておく必要があります。
修理代として一括で経費計上できない場合がある
事業用の車を修理した場合、多くは修繕費として処理できます。たとえば、壊れた部品を交換したり、傷んだ部分を直したりするような修理です。
ただし、修理とあわせて性能を大きく向上させるような改造を行った場合は注意が必要です。このような支出は資本的支出とされ、資産として扱う必要があります。資本的支出は一度に全額を経費にできず、耐用年数に応じて減価償却で少しずつ経費化するルールになっています。
判断が難しい場合でも、次の条件に当てはまれば修繕費として処理することが可能です。
●1回の支出が60万円未満である場合
●支出額が車両の取得価額(前期末の帳簿価額)の10%以下である場合
出典:国税庁「No.5402 修繕費とならないものの判定」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm)
勘定科目の統一に注意が必要
車の修理代を処理するときによく使われる勘定科目は修繕費か車両費です。どちらを選んでも間違いではありませんが、重要なのは一度決めた科目を継続して使うことです。
たとえば、ある年はタイヤ交換を車両費で処理し、翌年は修繕費で処理するといったようにばらつきがあると、帳簿の一貫性がなくなります。その結果、税務署に「なぜ処理方法を変えたのか」と疑問を持たれる可能性があります。
安心して会計処理を進めるためにも、早めに会計方針を決めておき、同じ勘定科目で統一して処理することが大切です。
私用でも同じ車を使っている場合は「家事按分」が必要になる
事業用の車をプライベートでも利用している場合、修理代を全額経費にはできません。たとえば平日は仕事に使い、休日は家族の送迎や買い物に使うといったケースです。
このような場合には「家事按分」という考え方を使います。事業と私用の利用割合を計算し、その割合に応じて修理代を経費に計上する方法です。
たとえば、利用の半分が仕事、半分が私用であれば、修理代の50%だけを経費にできます。割合を出すときは、走行距離や利用時間といった客観的な基準をもとにすると税務署に聞かれた際も説明がしやすく安心です。
経費計上が必ずお得になるわけではない
経費にできれば「節税になって得」と思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。確かに経費に計上すると利益が減り、結果として税額も少なくなります。しかし修理代そのものは現金の支出であり、支払ったお金が戻ってくるわけではないのです。
節税効果より出費のほうが大きければ、手元資金は減ってしまいます。だからこそ「経費にできるかどうか」だけでなく、修理代や日々のメンテナンス費をどう抑えるかという視点も重要です。
節税とはお金を増やす手段ではなく、必要な支出を正しく処理し税負担を軽減するものです。無駄な出費を減らし、本当に必要な部分に資金を充てることこそ、会社に現金を残す近道といえるでしょう。
損害賠償金は経費に計上できる?
事業を行ううえで発生した損害賠償金も経費として処理できる場合があります。
そもそも経費とは、事業活動を続けるために必要な支出です。仕事中に起きた事故や業務に関連するトラブルで支払った損害賠償金であれば、事業に関わる支出とみなされ、経費に計上できる可能性があります。
たとえば、会社で使っている車を運転中に追突事故を起こし、相手方の車の修理代を会社が負担したケースです。業務に必要な行動の結果と判断されやすく、経費として処理できます。
その際、修理代だけでなく、慰謝料や示談金、見舞金などについても、必要経費として認められる場合があります。
出典:国税庁「No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1710.htm)
経費にできたときの仕訳と勘定科目
では、損害賠償金を経費として処理する場合、どの勘定科目を使えばよいのでしょうか。
多くのケースで使われるのが「雑損失」です。雑損失は、思いがけず発生した損害や突発的な出費を処理するときに使う科目で、損害賠償金もここで処理するのが一般的です。
具体例で見てみましょう。業務中に追突事故を起こし、相手の車の修理代として15万円を小切手で支払った場合、仕訳は次のようになります。
(借方)雑損失 150,000 /(貸方)当座預金 150,000
経費に計上する時期
損害賠償金を経費にする際に大切なのは、いつ計上するかというタイミングです。状況によって扱い方が変わるので注意しましょう。
1. 交渉中の場合
金額がまだ確定していない段階では、原則として経費に計上できません。ただし、自社が相手に「この金額を支払う」と正式に提示している場合は、未払金として処理できます。その際は、通知書やメールなど、金額を提示したことを証明できる書類を残しておくことが大切です。
2. 合意済みの場合
相手方と合意が成立した時点で、支払い義務が確定します。この場合は、確定した金額を雑損失として計上するのが一般的です。
3. 分割払いの場合
分割払いに合意している場合は、支払期日が来て初めて債務が確定します。そのため、総額を一度に未払金として計上できません。各回の支払期日が到来するごとに、その分を仕訳する必要があります。
つまり、損害賠償金は債務が確定したタイミングで計上するのが基本ルールです。交渉中であれば未払金として扱い、合意済みなら確定額を計上し、分割払いなら期日ごとに仕訳を行うと覚えておくと安心です。
損害賠償金を経費にできないケース
仕事に関わる事故やトラブルで支払った損害賠償金は、基本的には経費にできます。しかし、すべての場合が認められるわけではありません。
たとえ業務中の事故であっても、加害者に故意や重大な過失がある場合には経費になりません。通常の事業活動のリスクではなく、本人の責任で発生した出費とみなされるためです。具体的な例としては、酒気帯び運転や信号無視、極端なスピード違反などがあります。
さらに、会社側に問題がある場合も同様です。たとえば、事業主が従業員に過積載を強要したり、整備不良の車を運転させたりした場合は、会社の指示自体が重大な過失と判断されます。
また、プライベートでの事故による損害賠償金も対象外です。休日のドライブや遊びに出かけた際の事故は業務と関係がなく、完全に本人の責任で生じた支出だからです。法人が立て替えて支払ったとしても、経費にはできません。
出典:国税庁「No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1710.htm)
経費にできなかったときの仕訳と勘定科目
経費にならない損害賠償金を会社が一時的に支払った場合は、立て替えとして処理します。仕訳では貸付金を使い、従業員から返済を受ける前提のお金として扱います。
【仕訳例】
従業員が私用で事故を起こし、相手方の修理代20万円を会社が小切手で支払った場合
(借方)貸付金 200,000円 /(貸方)当座預金 200,000円
損害賠償金を回収できない場合
立て替えた損害賠償金は最初に貸付金で処理しますが、従業員に支払能力がない場合には回収不能と判断されます。その時点で、返済されなかった分を貸倒損失として経費に計上できます。
仕訳の流れは次のようになります。
1.立替払いをしたとき
借方:貸付金 1,000,000円 / 貸方:当座預金 1,000,000円
2.一部返済を受けたとき(20万円)
借方:現金 200,000円 / 貸方:貸付金 200,000円
3.残りの80万円が回収不能となったとき
借方:貸倒損失 800,000円 / 貸方:貸付金 800,000円
立て替えた時点では貸付金で処理し、返済不能と確定した時点で貸倒損失に振り替える流れになります。
まとめ
車の修理代は、基本的にすべて経費にできます。ただし、性能を高める改造や寿命を延ばすような修理は資本的支出となり、その年に全額を経費にはできません。減価償却で耐用年数に応じて少しずつ費用化する必要があるため注意が必要です。
修理代を経費にできれば節税になりますが、修理費用そのものは現金の支出です。節税効果だけに目を向けるのではなく「必要な修理なのか」「もっと効率よく直せないか」といった視点を持つことも大切です。
とはいえ「直したいけれど修理費が高そう」「どこに頼めばいいか分からない」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。そんなときは、全国1,300店舗以上のネットワークを誇る「ピッカーズ」にお任せください。
ピッカーズは、自社工場で修理するためリーズナブルな価格での仕上がりを実現しています。「早く・キレイに・安く」にをモットーにクルマのキズとへこみを直します。
また、ガソリンスタンド併設店なら給油のついでに依頼でき、全国チェーンならではの信頼感も魅力です。まずは「ピッカーズ」で検索して、お近くのピッカーズ店をお探しください。